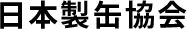
食缶の材料であるぶりきは、耐食性、はんだ付け性、加工性、外観の良さ、その他長い実績による信頼性などにより、缶詰の発明当時から主流 の地位を保ってきました。しかし、ぶりきに欠くことのできないスズは、産出国が東南アジア諸国やボリビアなどに限られているため、第2次 世界大戦では深刻なスズ不足を体験しました。 また、これらの諸国は慢性的に政情が不安定なこともあり、しばしばスズの供給不足が起きて価格が高騰することや、スズ資源もやがて枯渇す るものと見られていることなどから、第2次世界大戦を契機に従来のスズメッキ量の多い熱漬ぶりきから、メッキ量の少ない電気ぶりきへ変 わっていったのです。 一方、このようなスズ使用量を減らしてぶりきを製造する方法とは別に、スズを全く使用しない缶材料の開発が缶詰を生活必需品としているア メリカで強く要望されるようになり、研究が進められました。その結果開発されたのが、スズメッキの代わりに鋼鈑表面を化学処理したティン フリー スチール(スズがメッキされていない鋼鈑という意味)、略してTFSなのです。 ぶりきに代わる新しい缶材料には、少なくとも次のような特性が要求されます。
①貯蔵中や搬送中に錆が発生しないこと。
②塗装や印刷仕上げでは表面がよく濡らされ、アイホールなどの表面欠陥を発生させないこと。
③塗装焼き付け後、絞り加工などの成形の際、塗膜剥離を起こさないこと。
④塗装加工後、内容物に対して耐食性が優れていること。
⑤はんだ付けに劣らない高速接合が可能であること。
このような缶材料に要求される諸特性をある程度満たすものとして、アメリカで注目された化学処理鋼板の一つが浸漬クロム酸処理によるハイ
ナック材です。この板材が液体洗剤容器としてぶりきより優れていることがわかり、1950年に本格生産が開始されました。また、1956年には、
この方法に対抗して無水クロム酸溶液の陰極還元によって形成される陰極皮膜を鋼板の表面に処理に利用する方法が考案され、電解クロム酸処
理法による生産が開始されました。
日本でも1956年頃から電解クロム法の開発が進められていましたが、1961年に東洋鋼鈑のハイトップが工業化され、現在のTFSの量産が開始さ
れたのです。
ハイトップは、ぶりき、ローモ板(ブラック プレート)に代わって美術缶、その他家庭用品などの分野に広く使用されてきました。その後、
1962年に富士製鐵(現日本製鐵)のクロムメッキ鋼鈑キャンスーパーが、また1972年には日本鋼管(現JFEスチール)のブライトコートが本格
生産され、さらに1976年には川崎製鉄(現JFEスチール)も生産を開始しました。


こうした鋼材の開発とともに、製缶方法の開発が進みアメリカでは、1966年アメリカ・キャン社によってナイロンを接着剤として製胴するミラ
シーム法が、溶接缶では1967年にはコンチネンタル・キャン社によってコノウェルド法が誕生した。
日本では1970年に東洋製罐がナイロンフィルムを接着剤とするトーヨーシーム法を開発した。それまで、缶詰用の缶は缶胴のサイドシーム部の
接合方法として缶胴材の両側端部を折り返して嵌合させたロックシーム(Lock Seam)をはんだ付けする方法が一般的であったが、これにより
飲料分野での大きな飛躍をみた。
現在は缶胴材の両側部を重ね合わせたラップシーム(Lap Seam)を溶接により接合する方式の溶接缶が一般的になっている。
溶接缶は20世紀の初めには既に市場に現れていたと言われるが、次のような問題点があり一般的には普及されなかった。
(1)手動式機械のため生産数量が限られていた。
(2)職人の技術によって、製品の品質が左右された。
(3)溶接時、高温のため溶けたすずで電極が汚れたり、摩耗したりして電極の寿命が短く、品質も不安定であった。
溶接缶の代表的なものとして、アメリカのコンチネンタル・キャン社のコノウエルド缶とスイスのスードロニックAG社の溶接缶があげられる。

スードロニックAG社は1959社に上下溶接電極を回転ロールにし、そのロール表面に一条の溝を設け、この溝に中間電極となる銅ワイヤーを走行させて移動電極として作用させる新しい技術を開発した。この方式は溶融すずや酸化物、その他の不純物は中間電極の銅ワイヤーに付着するので電極の汚れがなくなり、品質の均一な溶接が得られるようになり溶接缶の用途が急速に拡大されるようになった。
1975年スードロニックAG社がWIMA(ウイマ:Wire Mash)方式という溶接部の重ね合わせ部を極端に狭くした溶接方式を開発したことにより、食品・飲料缶分野への溶接缶の適用が可能となり、現在では各種飲料缶、食缶、エアゾール缶、18L缶、一般缶(茶、菓子などのドライパックもの、モーターオイル缶など)等多岐にわたっている。
わが国においてもスードロニックAG社から溶接技術を導入すると共に缶内面溶接部の補修技術を開発し飲料へ展開して拡がり、1978年トマトジュース、果実飲料、コーヒー飲料向けに本格的に展開された。また1984年からは、食缶(魚、畜肉類、果実類、蔬菜等)へも採用された。1993年には、大和製罐ならびに北海製罐は、缶胴の内外面をペットフィルムでラミネートした3ピース缶の生産を開始した。
缶には天蓋と缶胴とで構成される2ピース(2-piece)缶がある。この技術も古くから開発されており、1847年テイラー(A.Taylor)により開発され、楕円缶、角缶などが代表的なものとされる。
この製缶技術は、楕円缶や角缶のように缶径対缶高の比が1対1以下の浅絞り缶(Drawn Can)を作る浅絞り加工法と、缶径対缶高の比が1対1ないし1対1.5程度のプリン缶ならびにツナ缶など深絞り缶(Deep Drawn Can)を作るドロウ・アンドリドロウ法(Draw&Redraw Method)といわれる深絞り加工法の2種類がある。
これらの加工技術には、異形缶やシームレス缶が容易に製造でき、かつ設備費が少ないなどの利点がある一方生産性が低くまた材料歩留まりが低いなどの欠点があった。このため、高速の生産と低コストが要求され、缶の高さが望まれる飲料用の容器の製造には不向きであり、ほとんど活用されなかった。
しかし1961年アメリカ・キャン社(ACC)はインパクト・エクストルージョン法(Impact Extrusion Method)と呼ばれる新しい深絞り技術でブリキ製のエアゾール缶の製造技術を確立し、ミラフロー缶(Mira Flow Can)を開発した。
またクアーズ社(Coors Co.)は、1965年インパクト・エクストルージョン法を改良してアルミ製の製造技術を確立し、世界で初めてアルミ製2ピースの缶ビールを上市した。
インパクト・エクストルージョン法といわれる深絞り加工技術は、高純度のアルミスラブを用い、金属押出チューブの製造法と同様に、衝撃押出し用のプレスでパンチとダイの間より金属素材を押し出す冷間加工により、缶胴の壁厚を均一にした耐圧容器を作る方法である。本方法には、ビール、エアゾール缶などの製造に適しているリバースインパクト・エクストルージョン法と、歯磨きチューブの製造に適したフォーワード法とがある。
製缶速度は毎分45〜80缶程度であるが最近は製缶能力があがり毎分200缶以上の製缶機が開発されている。
本法は①1工程でできる。②缶径対缶高比が1対10以上などの缶高の製造が可能である③異形缶が製造可能であるなどの長所がある。
一方、①缶底ならびに缶胴壁を薄くするのに限度がある②材料の使用量が多く、缶重量が大きい③缶胴壁表面の肌荒れが多い④缶のコストが高いなどの欠点があった。
このため、ビール、炭酸飲用としての用途の道が開けたとはいえなお依然として3ピース缶が主流を占めていた。
その後、インパクト・エクストルージョン法の欠点をカバーするドロー・アンド・アイアニング法(Draw&Ironing Method)といわれる新しい深絞り技術が登場した。この技術は1940年代にスイスのJ.Kellerの発明したKeller Pressによって、黄銅板から薬莢(やっきょう)を製造したことに端を発するといわれている。このしごき加工を缶の製造に応用し、アメリカのW.V.Leeが、1945年にDI缶を開発した。缶詰市場への参入を目指していたアルミニウム業界は当時急成長してきたビール・炭酸飲料を対象にこのDI缶製法の導入を進め、1958年にカイザー社(Kaiser Industries)が試作を行った。1963年レイノルズ・メタル社(Reynolds Metal)がアルミ製のDI缶を初めてビール用に上市した。DI缶とはDrawn and Ironed Canのイニシャルを取った略称で、いわゆるドロー・アンド・アイアニング法により缶底と缶胴が一体成形された2ピース缶の一種であり、アルミ製とスチール製がある。
1973年には、アメリカにおいてアメリカン・キャン社ならびにクラウン・コルク社(Crown Cork Co.)のスチール製DI缶がバドワイザー社(Budweiswr Co.)によりビール用に採用された。同時期に我が国においても大和製罐により、スチール製のDI缶が炭酸飲料、ビール用に開発されている。
さらに1994年には東洋製罐から内外面にポリエステルフィルムを施した薄肉化深絞り加工のスチール2ピース缶(TULC・・・Toyo Ultimate Can)が開発された。その後、アルミ製のTULCも開発され用途が広がっている。
この缶は従来のDI方式と異なって加工時に潤滑剤を使用しないドライ加工であり、内面塗料が不要な為、塗料焼き付けによるCO2の排出量が大幅に削減されるとともに洗浄工程がなく、排水処理が不要なため、今日における地球環境問題を先取りした容器として注目されている。
大和製罐はPETボトルが伸長した要因をリシール性及び持ち運びの利便性と考え、金属缶本来の長所である内容物保護性(遮光性・酸素バリア性・ガスバリア性等)にリシール性を付加したボトル型アルミ缶を2000年に開発し、スチール缶の主要用途であるコーヒー分野をターゲットとして、2005年にボトル型スチール缶を開発した。
一方、東洋製罐はTULCを基本缶とし「開けやすく・飲みやすく・香り漂う」をコンセプトに清涼飲料用に従来のイージーオープン蓋に代わってキャップを付与したスチールボトル缶を2004年に開発した。
また、武内プレス工業(株)が2000年、三菱マテリアル(株)(現アルテミラ製缶(株))が2001年、昭和アルミニウム缶(株)(現アルテミラ(株))が2004年、東洋製罐(株)が2018年にそれぞれボトル型アルミ缶(2ピース構造)の製造販売を開始した。

我が国では、1965年(昭和40年)4月からビール缶がアルミのプルトップを付けて登場。
それまでは、ビール缶や炭酸飲料は高い内圧に耐えるように蓋には硬いブリキが使われてきており、付属の缶切りで開けていたが、時折、ビールが吹き出したりして課題が残されていた。
プルトップ蓋はふたの中心部を張り出して作ったリベットにアルミ製のタブをかしめて固着し、このリベットを囲んでスコアをいれたものであったが、タブが長方形に加工されたものであった。その後1967年タブがリング型になると同時にリベット径も小さくなり一段と開口しやすくなった。
イージーオープンエンドはビール缶に引き続き、炭酸飲料用の缶にも使用された。

1969年〜1970年にかけ、ジュースやネクターにも採用されるようになり、さらに様々な飲料に展開されるようになった。また、トマトジュースの様な塩分を含んだ飲料は穿孔の問題からブリキ製のイージーオープン蓋の開発がすすめられ、1973年には塩分を含んだトマトジュース等の飲料へも展開されるようになった。
その後、塩分に対しても耐食性能が高いアルミ材の開発と内面塗料の改良によりアルミ蓋での展開も可能となり、ほぼすべての飲料でアルミイージーオープン蓋が採用され簡便性がより促進された。
1990年頃プルタブの投げ捨てによる、ごみの散乱が社会問題となりステイオンタブ(SOT)蓋に切り替わった。ステイオンタブ蓋とはタブを引き起こし戻すと飲み口が開くがタブ自体が缶体からはずれない機構になっており、現在はほとんど全ての飲料缶で採用されている。
飲料以外の缶詰にもイージーオープン化への要望が高く、小型缶を中心にフルオープン蓋が開発普及している。
フル・イージーオープン蓋はプルタブを引っ張るとフタ全体がスコアからちぎれ開口する機構になっており、固形物等が缶から簡単に取り出せるようになり、缶切り無しで台所で使用する利便性を高めるとともに、ピクニックや屋外でのバーベキューにおいても缶詰の使用機会が増えている。