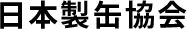

ブリキ缶は最初の頃、鋏(=はさみ)と篭手(=こて)とによって手で作られ、細工師はまずブリキ板を長方形に切りこれをまるめてその両端をつき合わせその継ぎ目に沿って約3mm厚さに、はんだを盛り上げて接合して缶胴とし、別にブリキ板を円形に切り抜いたものを缶胴の一方の端に底としてのせ、缶胴と同じようにはんだを盛り上げて接合した。
この缶に食品を詰め、底と同じ円形のブリキ板をその上に置いてはんだ付けして、これを沸騰水のなかに入れて内容物を十分加熱し、膨張した蓋に小孔をあけて脱気し、最後に缶がまだ熱いうちにこの小孔をはんだで塞いで缶詰とした。
ほどなく、はんだ付け方法は改善されて、缶胴はその両端が重ね合わされてはんだ付けされるようになり、また蓋底も円形に切り抜いた板を丸い棒の上にのせて、その縁をたたいて折り曲げたものとなり、これが缶胴にはめられてはんだ付けされるようになり、缶の外観がよくなると同時にはんだの使用量もいちじるしく減った。しかしこの頃の製缶能力は一人一日わずか60~70缶に過ぎなかった。
1812年にピーター・デュランドの特許をもとに、ブライアン・ドンキン(Bryan Donkin)とジョン・ホール(John
Hall)が世界最初の缶詰工場を設立し、翌年の1813年より陸海軍に納入を始めた。
ドンキン社の製品は、エドワード・パリー(Sir Edward Parry)が率いる北極探検隊に携帯された。当時の缶詰はブリキ板が厚いため「のみとハンマーで開けてください(Cut round on the top near the outer edge with chisel and hammer)」
と書かれていた。ブリキ缶詰はびんのように破損することがなく、輸送においても軽量で有利であった。しかし、びん詰に比べ高価になるため、軍需用、探検用などの特殊な用途に限られていた。
英国において発明されたブリキ缶詰を一大産業として開花させるのは、アメリカ大陸へ渡った移民達であり、殺菌、製缶、充填など急速な技術進歩が見られ、生産性を上げる機械化も同時に進んだ。
1825年トーマス・エー・ケンゼット(Thomas
A.kensett)が蓋にあらかじめ気抜孔を開けることを考案し、缶詰の製造方法とブリキ缶について、アメリカにおける最初の特許を得た。この考案により、缶詰の供給能力が大きく高まった。
1847年アメリカ人アレン・テーラー(Allen Taylor)は蓋底めんこ(End blank)の打抜機を発明し、2年後の1849年にヘンリーエバンス(Henrry
Evans)が打抜蓋底を発明し、それまで手で作られていた蓋底はここに機械で作られるようになり、それ以来缶に関する新しい考案や新しい製缶機の発明が相次いでなされた。
1852年に細工師のはんだごてに代わる最初の手動式はんだ付け機械で缶の底を缶胴にかぶせてその底の縁を溶融はんだ槽のなかに斜に浸し、手で缶を回転させてはんだ付けするいわゆるジョーカー(Joker)が発明された。
1869年缶胴をロック・シーム(Lock seam)する製胴機(Body forming machine)が発明され、缶胴接合部だけが手ではんだ付けされるようになった。
1876年ホーエ(Howe)がジョーカーを改善して自動式のものとし、米国の特許を得た。フローチング・マシン(Floating
machine)と称されるもので、これにより1人の工員が1日1,200缶のはんだ付けをすることができた。
1885年、缶胴接合部ははんだ付機(Side seam soldering machine)が発明され、これと前後して検缶機も発明され、ここに初めて全製缶工程が自動化された。
なお、蓋底を缶胴にかぶせて自動的に締め付けるクリンパー(Crimper)はすでにヨーロッパで1859年頃から使用されており、自動製缶機と組み合わせられることによって製缶能力が急速にあがり、1887年頃には製缶能力が1日当たり6,000缶に達するようになった。
この頃アメリカにおいて、最も多く缶詰として使用された缶はホール・アンド・キャップ式(Hole and Cap Type)外嵌缶(=そとばめ缶)、すなわち小蓋付外嵌はんだ付け缶であった。この缶には、食品は蓋にあけられた孔を通じて詰められ、ついでこの孔に小蓋(Cap)をかぶせ特殊なこてではんだ付けする。この蓋にはまた小さな気抜孔があり、缶が加熱脱気された後にはんだで閉じられ、最後に加熱殺菌が施されるというものであった。しかしこの小蓋付缶では、比較的大形片の食品を詰めることができないこと、肉詰前の空缶を効果的に洗浄することが難しかった。そしてこの不便さと缶詰の需要増大が、現行の2重巻締缶が誕生するきっかけとなった。
一方ヨーロッパのフランス、オランダ、スペインなどでは、缶胴の接合部以外には、はんだを使用せず、蓋底と胴との接合にはラバー・リングを入れ、クリンパーを使ってシングル・シームする方式のものが使われていた。 アメリカではチャールス・アムス(Charles Ams)が1888年にヨーロッパ方式の缶の改良研究を始め、1896年この缶で一番の問題とされていた分厚いラバー・リングに代わる液状ゴムの発明に成功し、特許をとった。
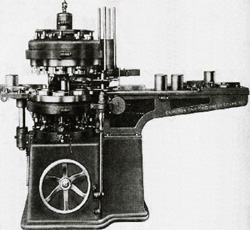
1897年にマクサム社の機械技師ジュリアス・ブレンジンガー(Julius Brenzinger)がこの液状ゴムを蓋底に塗布する自動機械を発明し、チャールスと力を合わせダブル・シーム(2重巻締)を考案した。 彼らはこの2重巻締缶は生産性が高まると同時に衛生的であることからサニタリー缶(Sanitary Can)と命名した。さらに缶詰業者ジョージ・ダブリュー・コブ(George W・Cobb)の協力を得てサニタリー缶を大量に製缶する自動機械を完成した。 その後自動製缶機も缶詰の需要増大とともに、大きな進歩を見せ1910年頃には1分間の製缶能力が120缶に達し、現在では1分間に1,500缶以上の能力を出すに至っている。
我が国には1913年(大正2年)初めてサニタリー缶の自動製缶機械が輸入され、1917年(大正6年)製缶事業が缶詰事業と分離し、現在ではほとんどの空缶は製缶事業者によって専門に作られ、缶詰事業者に供給されている。
それまでは、缶詰の製造業者が自家製造をしたり、お抱えのブリキ屋や飾り屋の職人に依頼していた。
食品の缶材料としては、主にブリキが使用されており、19世紀の初頭からの食文化のめざましい発展から、缶詰の需要が高まるとともに、ブリキの需要が著しく増加した。ブリキは薄鋼板にすずメッキしたものである。すずはその産地が東南アジア、ボリビアなどの国々に限られているため、米国では第二次世界大戦中に深刻なすず不足を経験した。これらの産出国は、慢性的に政情が不安定で、需要に応えられない状況も考えられ、さらに資源の枯渇も想定されたことから、第二次世界大戦を契機に電気メッキブリキ製造の技術が急速に発展し、メッキ量のコントロールが出来、すずの使用量が少ない電気メッキブリキへと変わった。